ミニチュアカー ミュージアム
自動車の歴史 時代/自動車メーカー別
Sorry Japanese Only
ミニチュアカー ミュージアム
自動車の歴史 時代/自動車メーカー別
TOYOTA PUBLICA (UP10) 1961 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.57m 全幅約1.42m エンジン 変速機: 水平対向2気筒 697cc 28HP 4段変速
性能: 最高速110km/h データーベースでトヨタ パブリカのミニカー検索
トヨタ パブリカ UP10型 日本 1961年
当時の通産省が検討していた国民車構想に沿って企画された小型車が1961年に登場したパブリカでした。車名はパブリックカー(Public car)からの造語で一般公募で選ばれました。軽量なフルモノコックボディに新開発のOHV強制空冷水平対向2気筒697cc(28HP)エンジン(U型)を搭載し、4段変速で最高速110km/hの性能でした。デザインは同時期のコロナ 2代目と良く似ていて、シンプルで良いデザインでした。
初期のパブリカはラジオ、ヒーターはもちろんフェンダーミラーすら無いという徹底した簡素化で38.9万円という低価格を達成していましたが、この実用一辺倒の仕様はあまり支持されませんでした。そこで1963年にラジオ、ヒーターなどを装備しクロームモール装飾を施したデラックス仕様(UP10D型)や、オープンカー仕様のコンバーチブルが追加され、人気を回復させました。1964年にはバンやトラックの商用車も設定されました。
1965年にパブリカをベースにした小型スポーツカーのスポーツ 800が登場しました。パブリカは1966年に排気量を800cc(36HP)に拡大し、ドライブトレーンや外観形状を変更する大幅な仕様変更が行われ、UP20型に変わりました。(実車画像→パブリカ UP20型) 販売価格を36万円に下げて当時の為替レート(1ドル=360円)では1000ドルになるため、1000ドルカーというキャッチフレーズで宣伝されました。1969年にパブリカ 2代目(KP30型)にモデルチェンジしました。
ミニカーは2002年に発売されたエブロ製で、初期型のUP10型をモデル化しています。プロポーションが良く、なんとなく安っぽい感じのする初期型のフロントの造形をうまく再現していて、非常に良い出来ばえでした。室内も良く再現されていて、フェンダーミラーが付いていないのも実車どうりです。当時物ミニカーとしてはモデルペットのUP10型とダイヤペットのUP20型がありましたが、どちらもレア物です。最近の物では国産名車コレクションのセダンとコンバーチブル、トミカ リミッテド、コナミの1/87などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ パブリカ 700 1961 (1/43 No.28)の画像です。メーカーはノレブで実車に即したカラーリングで、安価な雑誌付きミニカーながら上記のエブロ並みに良く出来ていました。ただコストの関係で室内の造形はエブロよりは少し簡素になっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は2012年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ パブリカ コンバーチブル 1964 (1/43 No.165)の画像です。こちらはメーカー名がミニカーに表示されていないのですが、イクソです。フェンダーミラー付きで室内などの細部もそこそこ良く仕上げてあり、これも安価な雑誌付きミニカーながら良い出来ばえでした。同じ型を使った物がFIRST43からも発売されていました。2018年に国産名車コレクション 1/24でもモデル化されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=966
MITSUBISHI 500 1961 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.14m 全幅約1.39m エンジン 変速機: 空冷4気筒 493cc 21HP 3段変速
性能: 最高速90km/h データーベースで初期の三菱車のミニカー検索
三菱 500 日本 1961年
戦前に三菱 A型を製作した経験があった三菱重工業は終戦後の財閥解体で東日本重工業、中日本重工業、西日本重工業の3社に分割されました。東日本重工業はアメリカのカイザーナッシュ社と提携し、コンパクトカー ヘンリー Jのノックダウン生産を1950年から始めました。1953年に東日本重工業、中日本重工業は三菱日本重工業、新三菱重工業に社名変更し、1953年に新三菱重工業でウィリス ジープのノックダウン生産が始まりました。1954年にはヘンリーJの本国での生産中止によりノックダウン生産が終わりました。(実車画像→ カイザー ヘンリー J)"
新三菱重工業は独自で自動車開発に着手し、水島自動車製作所(岡山県)が開発した軽3輪トラックのペット レオが1959年に発売されました。ペット レオは密閉式キャビンを採用し、4サイクル単気筒310cc(12HP)エンジンを搭載し、3段変速で最高速74km/hの性能で軽3輪車では最速でした。ペット レオは1962年まで生産されました。(実車画像→ 三菱 ペット レオ)"
1960年に新三菱重工業(名古屋自動車製作)は乗用車の三菱 500を発売しました。全長3.14m全幅1.39mの4人乗り小型車で、ボディはドイツのゴッゴモビルを参考にしたそうです。空冷4サイクル2気筒OHV 493cc(21HP)エンジンをリアに搭載するRR車で、3段変速で最高速90km/hの性能でした。モノコック構造のボディに全輪独立懸架サスペンションと、技術的には非常に先進的な車でした。当時の価格は39万円で1961年にはエンジンを594cc(25HP)に拡大しました。ただあまり人気がなかったそうで、1962年にはコルト 600に切り替わりました。コルト 600は500のボディーを拡大したもので、基本構造はそのままだったようです。(実車画像→ 三菱 コルト 600)
ミニカーは2012年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。メーカーはイクソで、実車の雰囲気がうまく再現されていてなかなか良い出来ばえでした。この車がミニカーになったのはこれが初めてで、この車をモデル化したことは国産名車コレクションの面目躍如といったところでした。(初期の国産名車コレクションはあまりモデル化されていないレアな車種を選択していました) なお量産ミニカーではないですが、三菱 500にはこの車の愛好者クラブが作成した少量生産ミニカーがありました。たぶん世の中にはこのような愛好者によって製作されたあまり知られていないミニカーが結構あると思います。 軽3輪トラックのペット レオは京商が1/43のポリストーン製ミニカーを2000年に発売していました。またトミカ リミッテドもレオをモデル化していました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)
"


以下は上述した三菱 500の愛好者クラブが作成したミニカーで1988年に発売されました。メーカーは不明で、縮尺1/43で材質はレジン製だと思われます。木製台座に「瀬戸大橋開通記念」と表記されていますが、瀬戸大橋が開通した際に三菱 500で渡り初めのパレードを行ったようです。その際に愛好者クラブが設立されたそうで、このミニカーはその設立記念品のようです。私は愛好者ではありませんでしたが、デパートで販売されていたこのミニカーを購入しました。(当時このような特殊なミニカーもデパートで売っていました、ただしプレミアム価格がついて18000円と高価でした) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はボディを取り外した内部の画像と梱包箱の画像です。ボディは簡単に外すことができ、再現されたリアエンジンを見ることが出来ます。梱包箱には実車の3面図が表示されています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1029
MITSUBISHI JEEP (J30) 1961 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.29m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 4気筒 2.2L 76HP 3段変速 パートタイム4WD
性能: 最高速95km/h データーベースで三菱 ジープのミニカー検索
三菱 ジープ J30型 日本 1961年
第2次大戦後にアメリカ軍が日本で軍用車を調達する為に、ウィリス製ジープを当時の中日本重工業(三菱重工業の前身)に生産させることになったのが、三菱製ジープの始まりでした。この車は戦後の警察予備隊(現在の自衛隊)で使用する小型トラックとしても採用されることになり、1953年からウィリス ジープ CJ3A型のノックダウン生産が始まりました。当初は左ハンドルでしたが、その後ウィリス製エンジンを国産化するなどして1955年にジープは国産化されました。"
当初の三菱 ジープの型式はJ1型で、構造はジープと同じはしご形フレームにリーフリジッド サスペンションで、パートタイプの4輪駆動方式でした。その後国産化された時の型式はJ3型となりました。1957年にエンジンをディーゼル化(2.2L 61HP)して世界初のディーゼルエンジン搭載ジープ JC3型が登場しました。1961年には右ハンドル仕様のJ3R型が追加されました。
その後2ドア ステーションワゴンやロングホイールベースで6人乗りの4ドア ステーションワゴンなどの日本独自のバリエーションが追加され、三菱のジープは防衛庁以外にも販売されました。1982年に一般ユーザー向けのパジェロが登場したことで、ジープは車種が縮小されました。1996年に防衛庁向けジープがパジェロ 2代目をベースにした73式小型トラックに切り替わり、ジープは1998年に生産中止となりました。(実車画像→ 三菱 73式小型トラック)"
ミニカーは2009年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。メーカーはイクソで、4ドアステーションワゴンのJ30型をモデル化しています。全体的に実車の雰囲気がうまく再現されていました。フェンダーミラーやフロントのウィンカーなどの灯火類や室内などの細部も良く再現されていて、安価な雑誌付きミニカーとしては申し分のない良い出来ばえでした。また三菱 ジープの乗用車タイプのミニカーはこれしかないので、車種的に貴重なミニカーでもありました。なお色違いの同じものがFIRST43でも販売されていますが、イクソ ブランドでは販売されていないようです。これ以外の三菱 ジープのミニカーとしては、トミカやトミカ ダンディのJ3R型、エイダイ グリップのJ52型などがありますが、すべてショートホイールベースをモデル化しています。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1931
GM CHEVROLET CORVAIR MONZA GT 1962 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.2m? 全幅約1.7m エンジン 変速機: 空冷水平対向4気筒 2.3L ターボ 102HP 4段変速
性能: 最高速 不詳 データーベースでモンザ GTのミニカー検索
GM シボレー コルベア モンザ GT アメリカ 1962年
GM シボレー コルベア モンザ GTは1962年に発表されたデザインを目的とした実験車でした。ベースとなったのはGMのリアエンジンのコンパクトカー シボレー コルベアで、エンジンをミドシップ配置に変更し未来的なスポーツカーに仕立てたもので、非常に魅力的なデザインでした。通常のドアはなく戦闘機のようにキャノピー部分を大きく開くことで乗り降りを行います。また尖ったボディ先端にあるヘッドライトのカバーが開いてヘッドライトが露出する構造は独創的でかっこいいです。なお一般的なドアを備えたオープンのロードスター仕様のモンザ SSも同時に公開されました。(実車画像→ GM シボレー モンザ SS)
モンザ GTをデザインしたのは日系人のラリー シノダ氏で、1968年に発売されたコルベット スティングレイ (C3型)にはこの車のイメージが感じられました。また1965年に登場したコルベアの2代目も、モンザ GTのイメージを実用車に落とし込んだスポーティな美しいデザインでした。GMはコルベアをフォード マスタングに対抗するスポーティカーに仕立てるつもりだったようです。ただハイパワーエンジンを搭載したコルベアは、リアエンジン車特有のオーバーステアでコントロールを失い横転する事故が多発して問題となり1969年に生産中止となりました。
ミニカーは1964年に発売された北欧デンマークのメーカーだったテクノの当時物です。(テクノは存続していますが、現在はオランダのメーカーとなっていて1/50のトラックのミニカーを作っています) 未来的な流線形デザインが見事に再現されていて非常に素晴らしい出来ばえでした。ヘッドライトカバーの開閉とキャノピーとリアカウルが開閉するギミック付きです。屋根がないオープン仕様(モンザ SSとは違う)もあり、カラーバリエーションが非常に多くありました。見た目がかっこいいことからかなり人気があったミニカーでした。当時のテクノのミニカーの最大の特徴は、初期の物は違いますが、分解/組立ができる構造となっていたことでした。(その為、その分だけ高価でした) このモンザ GTにもこの分解/組立ギミックが付いていました。当サイトのギミックのページでその詳細を紹介していますので、そちらも是非ご覧ください。→ テクノ モンザ GTのギミック紹介ページ これ以外のモンザ GTのミニカーは、このテクノ製をコピーしたオートピレンやジョアル、エーダイ グリップの1/28がありました。最近ではオートカルト(レジン製)がモデル化しています。 以下はフロント/ヘッドライト開閉の画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)
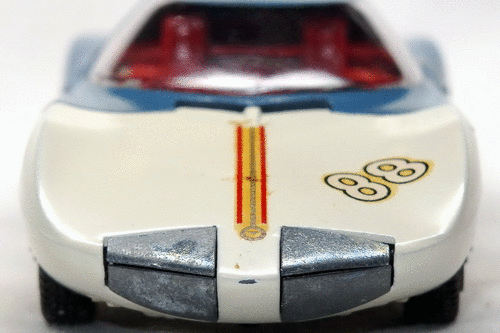

以下はバリエーションのモンザ GT スパイダー(1/43 型番931)の画像です。屋根がないだけであとは上記とほとんど同じです。これは光沢のある厚いクロームメッキがされていて、半世紀経過した今でもきれいな状態です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1801
FORD THUNDERBIRD SPORT ROADSTER 1962 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.2m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 300HP 3段自動変速
性能: 最高速203km/h データーベースでフォード サンダーバードのミニカー検索
フォード サンダーバード スポーツ ロードスター アメリカ 1962年
フォード サンダーバード 3代目が1961年に登場しました。デザインは未来の車をイメージしたというスタイリング 実験車 レバーカーのイメージを取り込んだ流線型の極めて斬新なものでした。(実車画像→ フォード レバーカー 1959) シンプルで独創的なフロントは今見ても魅力的ですし、ジェット機の排気口をイメージした丸型のリアライトはかっこいいです。300HPのハイパワー車でしたが、柔らかいサスペンションを持つ極めてアメリカ的な高級車でした。ハードトップとコンバーチブルの設定があり年間7万台以上も販売されるほど大ヒットし、フォード車のイメージアップに大きく貢献しました。
サンダーバードはT-BIRDと呼ばれ、当時の若者にも人気があったようです。1960年代のビーチ ボーイズの流行歌「FUN FUN FUN」の歌詞には父親のT-BIRDでドライブする娘の話が出てきます。1962年にはコンバーチブルのリアシートをFRP製のカバーで覆って2シータに見せかけた、スポーツ ロードスターが登場しました。またハードトップにビニールレザーを張りランドージョイント(開閉金具)を付けて開閉する幌風に見せかけたランドー仕様がハードトップに次ぐ人気となり、以後のサンダーバードにも継承されました。
ミニカーはフランクリン ミント製の1/43で、1991年に発売されました。これは1960年代の名車12台を1/43でモデル化した「1960年代のクラシックカー」シリーズの1台でした。(1950年代の名車をモデル化した「1950年代のクラシックカー」シリーズもありました) このシリーズは当時の定価が9500円と高価でしたが、ドアやボンネットが可動し、エンジンやシャーシのメカ部分が再現された当時最も精巧な1/43のミニカーでした。このミニカーはリアシートをFRP製カバーで覆ったスポーツ ロードスターをモデル化しています。ヘッドライトが透明プラスチック製でないところなどがややレトロな作風で、全体的にやや腰高のプロポーションでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きで、V型エンジンや室内のインパネなどがリアルに再現されていました。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。ボンネットの内側もきちんと塗装されていて、仕上げが丁寧です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


フォード サンダーバード 3代目のミニカーとしてはソリドの当時物、アンソンの1/18、 JOHNNY LIGHTNINGの1/64、最近のレジン製ではMATRIXなどがあります。ソリドは1963年にフォード サンダーバード ハードトップの当時物ミニカー(1//43 型番128)を発売していました。以下はその当時物 ハードトップの型をリファインして、1985年に発売された サンダーバード コンバーチブル(1/43 型番4504)の画像です。プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていて良く出来ていました。ボンネットが開閉するギミック付きで、エンジンが再現されています。室内は紙のシールでドアの内張を表現しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1988年に発売されたソリド製の フォード サンダーバード G.スポーツ (スポーツ ロードスター) (1/43 型番4517)の画像です。上述したコンバーチブルのバリエーションで、リアシートを覆うFRP製カバーが追加され、ホイールがワイヤースポークに変更されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=427
ページ « 前へ 1...123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ...373 次へ »
当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。
Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.