ミニチュアカー ミュージアム
自動車の歴史 時代/自動車メーカー別
Sorry Japanese Only
ミニチュアカー ミュージアム
自動車の歴史 時代/自動車メーカー別
LANCIA TREVI BIMOTORE 1984 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ランチア トレビ ビモトーレ イタリア 1984年
ファーストバックスタイルのランチア ベーターにトランクを追加してノッチバックセダンに仕立てたのがランチア ベーター トレビで1980年に登場しました。(1982年以降は単にトレビとなった) フロントのデザインなどはべーターと同じでしたが、ベーター シリーズの最上級仕様として、内装が豪華になりフォーマルなスタイルとなっていました。4気筒1.6L/2L(115HP)エンジンを搭載し、5段変速/3段自動変速で最高速180km/hの性能でした。
1981年に2Lに電子制御燃料噴射仕様2000IEが設定され、1982年にスーパーチャージャー付2L(135HP)エンジンを搭載し、チンスポイラーを付けた高性能版VX(ボルテックス)が追加されました。トレビは風変わりなインパネの不評などもあって、このクラスの高級車としては人気がなかったようです。1984年までに約4万台が生産されて、後継車のテーマにモデルチェンジしました。(実車画像→ ランチア トレビの風変わりなインパネ)
ミニカーはイタリアのミニカー付雑誌「LANCIA COLLECTION」のNo.69で、2014年頃にネットオークションで入手しました。メーカーはノレブで実車の雰囲気がうまく再現されていました。安価な雑誌付きミニカーながら、インパネなどの細部も良く仕上げてありました。このトレビ ビモトーレはラリー仕様車であったデルタ S4の4WDシステムの開発過程で作られたテスト車でした。ビモトーレとは2つのエンジンという意味で、後席部分にもう一つのDOHC ターボ 4気筒2L(150HP)エンジンを搭載し後輪を駆動していました。ミニカーは後席のエンジンを収めた四角い箱とリアドアに付いたリアエンジン用のエアインテークを再現しています。トレビのミニカーは同じ「LANCIA COLLECTION」のNo.32で高性能版のVXもモデル化されていますが、それ以外にはないようなので、これは貴重なトレビのミニカーの一つでした。この「LANCIA COLLECTION」にはこれまでモデル化されていなかったランチア車がいくつかありましたが、日本国内では入手が難しいようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1276
FERRARI TESTAROSSA 1984 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.51m 全幅約1.97m エンジン 変速機: DOHC V型12気筒 5L 390HP 5段変速
性能: 最高速290km/h データーベースでフェラーリ テスタロッサ 1984年以降のミニカー検索
フェラーリ テスタロッサ イタリア 1984年
フェラーリ 512 BBの後継車として、1984年にテスタロッサが登場しました。フェラーリの旗艦として、1960年代の名車 250 テスタロッサの名前を復活させました。TESTAROSSA(赤い頭)の伝統に従ってエンジンのカムカバーは赤く塗られました。ピニンファリーナによるデザインは512 BBの流れに沿ったものでしたが、サイドのエアインテーク部の大型フィンが並の車ではない迫力を感じさせました。エンジンは512 BBと同じDOHC V型12気筒5Lでしたが、4バルブ化されて360HPから390HPにパワーアップしていました。初期のモデルは運転席側サイドミラーがAピラーの中ほどに取り付けられていましたが、1986年以降は通常のドア前端部分に変更されました。
1991年に512 TR(テスタロッサの略)にモデルチェンジしました。外観的にはほとんど同じで、エンジンが425HPにパワーアップされ操縦性などが改良されていました。さらに1994年には512Mにモデルチェンジされました。MはModifiedのMで、521 TRの改良型という意味でした。電子式故障診断装置の追加、軽量化、車両剛性の向上などの改良がおこなわれました。外観的にはリトラクタブル ヘッドライトが固定式に、テールランプが丸型4灯になるなど大きく変更されました。エンジンは440HPとなり、最高速は315km/hとなりました。後継車は1996年に登場したフェラーリ 550 マラネロでした。
ミニカーは1988年に購入したウエスタン モデル製(ホワイトメタル製)の当時物です。ウィンドー/ライト類以外のほとんどの部品が金属製(ホワイトメタル)なので、ずっしりと重く存在感があります。特徴的なサイドのフィンやリアライト部分のルーバーが薄い金属板で作られていたので、実にリアルな質感がありました。当時の値段で13000円と高価でしたが、当時はこれ以上リアルなミニカーは無かったので思い切って買いました。初期のテスタロッサの特徴である左側のAピラーから生えているドアミラーが付属していて、これは自分で取付けました。これ以外のテスタロッサのミニカーはトミカ、ポリスティルの1/25、ブラーゴの1/18、マテルの1/18、ヘルパのプラスチック製の1/43、イクソ、ミニチャンプスの512TRと512Mなどたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1992年に発売されたヘルパ製のフェラーリ テスタロッサ タルガ (1/43 型番010313)の画像です。ヘルパは1/87のプラスチック製ミニカーがメインですが、少数ですが1/43(プラスチック/ダイキャスト)もモデル化しています。プラスチック製なのでプラモデルの組立完成品のようなもので、かなり良く出来ていました。(塗装はされていません) ドアと前パネルが開閉し、エンジンカバーが脱着でき、室内やエンジンがリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/前パネルを開いた画像とリア/エンジンカバーを外したエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1994年に発売されたミニチャンプス製のフェラーリ 512 TR (1/43 型番430072502)の画像です。ミニチャンプスらしいうまい造形でプロポーションは良く出来ていました。リアライトは透明プラスチックでルーバーと一体成型していましたが、このやり方ではウエスタン モデルのようにルーバーをリアルに再現するのは無理がありますので、そこが今一つでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1996年に発売されたミニチャンプス製のフェラーリ 512M (1/43 型番430074120)の画像です。上述した512 TRをベースにして、ヘッドライトを固定式に、テールランプを丸型4灯に変更していました。また室内の造形が512 TRより丁寧に仕上げられていました。このミニチャンプスに限りませんが、室内の仕上げに自信があるミニカーは、室内がよく見えるようにサイドウィンドーを開いた状態にしてあるものが多いです。この512Mも室内のの仕上げが良いのでサイドウィンドーが開いていました。上記のミニチャンプス製の512 TRは室内の仕上げレベルが少し落ちる(それでも結構リアル)ので、サイドウィンドーが閉じていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


"
このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1234
LAMBORGHINI LM002 1984 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.95m 全幅約2m エンジン 変速機: DOHC V型12気筒 5.2L 455HP 5段変速
性能: 最高速203km/h データーベースでランボルギーニ L002/チーターのミニカー検索
ランボルギーニ LM002 イタリア 1984年
1976年にランボルギーニはBMWからミッドシップ車 M1の開発/シャーシ製造を依頼され、1977年にはプロトタイプが完成しました。しかしランボルギーニの財政状況の悪化で、製造が遅れたことでランボルギーニは委託契約を破棄され、結局1978年に倒産しました。その後ランボルギーニはイタリア政府の管理下となり、1987年にクライスラー傘下となるなどして、1999年からはフォルクスワーゲン/アウディ グループの一員となっています。
ランボルギーニはオフロード車のプロトタイプをチーター(CHEETAH)という名前で1977年に発表しました。この車はアメリカのMTI(Mobility Technology International)社の依頼でアメリカ軍向けの軍用車として開発され、クライスラー製のV型8気筒エンジンを横置きでリアミッドシップ搭載していました。しかしこの車は軍用車として採用されませんでした。(実車画像→ ランボルギーニ チーター)
そこでこの車は富裕層向けのオフロード車として再設計され、1981年にLM001という名前のプロトタイプが製作されました。LM001はリアエンジン車特有の加速時の操縦性に問題があり、エンジンをフロント搭載に変更して完成したのがLM002でした。豪華な内装や装備を持つ4人乗り高級車で、ボディ後部はピックアップのような荷台になっていました。駆動方式は副変速機を持つフルタイム4WDで、タイヤはパンクしても走行可能なピレリ製の特注品でした。当初のエンジンはカウンタック用を改良したDOHC V型12気筒5.2L(455HP)でした。1993年まで約300台が生産されました。(なお市販されたのは1986年とする資料が多いですが、1982年からとする資料もあります)
ミニカーは2004年に発売されたミニチャンプス製です。ミニチャンプらしい手堅い作りで、角ばったボディや床下部分のサスペンションなどの細部もリアルで、全体的に実車をリアルに再現してありました。室内などの細部も彩色され良く再現されていました。これ以外のLM002のミニカーは京商の1/18と1/64、イクソ(廉価版のホワイトボックス)などがあります。プロトタイプのチーターのミニカーは、Bブラーゴ、ダイヤペット、トミカがありました。チーターは実際には販売されなかったので、ミニカーはいずれもショーカーをベースにした創作的なものになっていました。以下はフロント/リアの拡大画像と床下部分の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1992年に発売されたダイヤペット製のランボルギーニ チーター 4WD ビックタイヤ (1/38 型番T93)の画像です。ビックタイヤという名前が付いているだけあって、巨大なタイヤがついています。当時トヨタ ハイラックスなどの4WD車に大きなタイヤを付けた改造車(アメリカではモンスタートラックと呼ぶ)が流行っていて、その流行りに乗ってダイヤペットがビックタイヤという名前を付けた4WD車のミニカーをいくつか出していました。(トヨタ ランドクルーザー、トヨタ ハイラックス、日産 テラノなど) これもその一つで、リアルな実車があったわけではなくお遊びのミニカーですが、時代を反映した面白いミニカーでした。なおビックタイヤは現実離れしていましたが、ボディはチーターをそれらしく再現していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1230
TOYOTA HILUX 4WD (50/60/70) 1984 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トヨタ ハイラックス 4WD (50/60/70系) 日本 1984年
1983年にハイラックス 4代目(50/60/70系)が登場しました。後輪駆動車にはポピュラーシリーズとコンフォタブルシリーズの2タイプがありました。ポピュラーシリーズは先代のボディが継続生産され、コンフォタブルシリーズと4WD車はボディを一新しました。新しいボディは前後のブリスターフェンダーが特徴でした。後輪駆動車のエンジンは4気筒1.6L/1.8Lガソリンと4気筒2.2L/2.4Lディーゼルエンジンで、4WD車は4気筒2Lガソリンと4気筒2.4Lディーゼルエンジンが搭載されました。ディーゼルエンジンにはフロアシフトの4段自動変速機が設定されました。
1984年に4WDモデルをステーションワゴン化したトヨタ初のSUV ハイラックス サーフ(輸出仕様の名前は 4ランナー)が追加されました。1985年に乗用車系のハイラックス サーフの前輪サスペンションは独立懸架方式に変更されましたが、ピックアップの前輪サスペンションは悪路に強い頑丈なリジット方式のままでした。1988年にハイラックス 5代目(80/90/100/110系)にモデルチェンジしました。 (実車画像→ ハイラックス 5代目 1988)
ミニカーは1985年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットの協力工場の11番工場製で、ハイラックス 4代目の4WDをモデル化しています。ダイヤペットは先代を型番T3でモデル化していましたので、その型を変更してハイラックス 4代目に仕立てているようです。フロントグリル、ブリスターフェンダー、フロントのウインチなどをかなり大幅に変更していました。その変更でハイラックス 4代目の雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/リアパネル(後アオリ)が開閉するギミック付きです。当時市販車を少し改造して、このような大きなタイヤを履いたハイラックス 4WDは実在していて、実車をまじかで見たことがあります。なおダイヤペットはさらに大きなタイヤを付けた ハイラックスを型番T66(以下の画像参照)でモデル化していましたが、さすがにそんな大きなタイヤの実車は実在しなかったようです。(映画用などの特殊な改造車ならあったようですが) これ以外のハイラックス 4代目のミニカーはトミカとマッチボックス(スーパーキング シリーズ)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/リアパネル開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は上述した1987年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ ハイラックス 4WD ビッグタイヤ (1/40 型番T66)の画像です。このハイラックス ビッグタイヤの画像はダイヤペットのカタログから流用しました。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1664
TOYOTA MR2 (AW11) 1984 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.95m 全幅約1.67m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.6L 130HP 5段変速/4段自動変速
性能: 最高速197km/h (輸出仕様) データーベースでトヨタ MR*のミニカー検索
トヨタ MR2 AW11型 日本 1984年
日本初の量産ミドシップ スポーツカー トヨタ MR2が1984年に登場しました。1983年の東京モーターショーで試作車SV-3が公開され、翌年に若干の仕様変更がされて量産化されました。(実車画像→ トヨタSV-3 1983) 当時の流行りだったリトラクタブルヘッドライトを持つ角ばったデザインは、個人的にはスポーツカーとしてはやや地味だと思いました。コストダウンの為、エンジンと変速機は前輪駆動のカローラ 80型の物を流用し、それをミドシップ搭載していました。1984?の日本 カー オブ ザ イヤーを受賞しました。
1986年のマイナーチェンジで後期型となり、スーパーチャージャー付エンジン(145HP)が追加され、Tバールーフ仕様が設定されました。1989年まで生産され、MR2 2代目 SW20型にモデルチェンジしました。当時のWRC用ラリーカー セリカ(TA64型)の後継として、AW11型をベースにして4WD化したラリーカー(開発コード 222D)が開発されましたが、レギュレーションが変更されたことなどからWRCに参戦することはありませんでした。
ミニカーは1984年に発売されたダイヤペットの当時物です。ダイヤペットの協力工場の144番工場製で、この144番工場は当時としてはリアルな造形のミニカーを作っていました。このMR2もプロポーションがやや腰高な感じですが、全体的にかなり良い出来ばえでした。フロントトランク/ドア/リアボンネットが開閉するギミック付きで、リトラクタブルヘッドライトも可動します。フロントにはスペアタイヤ、リアにはエンジンが再現されていました。またこの2トンカラーは当時としては綺麗に仕上がっていました。(塗装が経年変化で多少荒れていますが) これ以外の当時物ミニカーとしては、トミカのSV-3、トミカ ダンディのSV-3がありました。当時物以外では、Mテック、Mテックの型を使ったトサ(TOSA)コレクション、エブロ、CM'Sの222D、イクソ プレミアムXのラリーカー仕様 222D、国産名車コレクション、レジン製ではMARK43などがあります。 以下はフロント(トラクタブルヘッドライト開閉)/フロントトランクを開いた画像とリア/リアボンネットを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1985年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 トヨタ SV-3 (1/43 型番DJ07)の画像です。これは試作車のSV-3をモデル化していますので、量産車のMR2とはリアスポイラー形状とTバールーフが異なっています。当時のトミカ ダンディは従来の国産ミニカーとは一線を画すリアルな造形が特長でした。このSV-3も実車をリアルに再現してありかなり良い出来ばえでした。(ただフォグランプなど灯火類の造形はやや簡素ですが) フロントトランク/ドア/リアトランクの開閉とリトラクタブルヘッドライトが可動するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)/フロントトランクを開いた画像とリア/リアトランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)
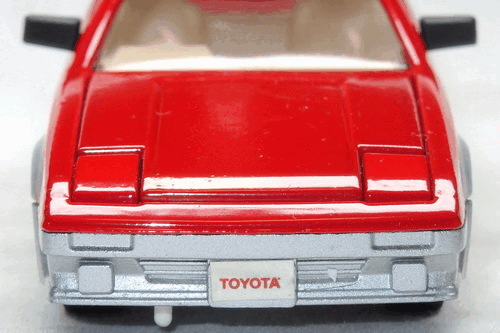

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ MR2 (1/43 No.43)の画像です。メーカーはノレブで、ノレブらしいそつのない造形でプロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。彩色はされていませんが、室内も良く再現されていて、安価な雑誌付きミニカーながらとても良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)



